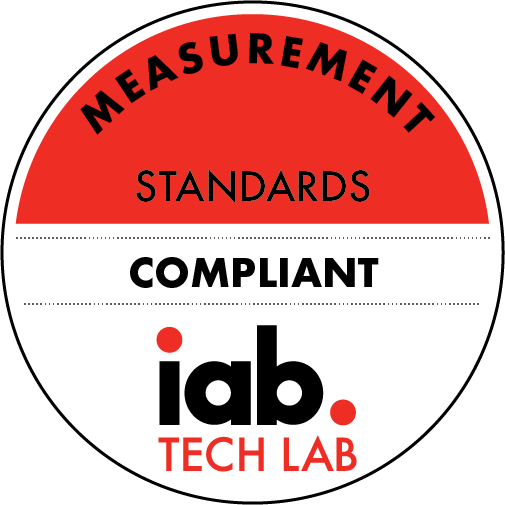意識と神経とアルゴリズム 第十一回『感覚の代行と拡張』デイビッド・イーグルマン「あなたの脳の話」より
Description
2007年、ラムッスン脳炎による発作で苦しんでいたキャメロン・モットという少女が、12時間の神経外科手術のすえ、脳の半分を摘出されました。しかし、手術後も彼女は体の片側が弱いだけで、他の子どもたちと同じように言語、音楽、数学、物語を理解でき、スポーツにも参加することが出来ました。脳の残り半分が失われた機能を引き受け、神経の配線をし直し、ほぼ全ての働きが半分のスペースに押し込まれたのです。このように、新しい状況に順応して学ぶたびにみずからを変えるという脳の可塑性が、テクノロジーと生物学の融合を可能にします。
人工内耳は、外部マイクロホンが音声信号をデジタル化して聴覚神経に送り、人工網膜は、カメラからの信号をデジタル化して目の後ろの視神経につながれているグリッド電極に送ります。現在、何十万という聴覚・視覚障害者がこうした装置で自分の感覚を取り戻しています。初めのうち異質の電気信号は脳にとって理解不能ですが、やがて神経ネットワークは入ってくるデータのパターンを抽出し、大ざっぱでもそれを理解する方法を見つけ、他の感覚と相互参照し合って入ってくるデータの構造を探り出し、数週間後には情報が意味を持ち始めるのです。
脳という汎用の計算装置は、入ってくるどんな情報でも活用できるアルゴリズムを構築し様々な感覚を生み出します。そこで、私たちの五感やバランス感覚、温度の感覚などで捉えることのできないものを直接脳に送り込むことを可能にすれば、人間にも紫外線や赤外線や超音波に反応する感覚が身につけられるかもしれません。デイヴィッド・イーグルマンは、小さな振動装置で覆われているべストを作りました。身に着けていると音のデータストリームが胴体に伝わる振動パターンに感覚代行され、5日も経つと話されている言葉が特定できるようになるのです。
感覚は拡張することも可能です。スマホの画面を見ることなく、インターネットの天気や株価のデータを脳で直接理解できるようになるかもしれません。ただ新しい感覚を持つだけでなく、新しい運動を作り出すことも可能です。脊髄障害で筋肉の動かなくなったジャン・シュールマンは、左運動皮質へ2個の電極を埋め込むことで、ロボットアームを動かせるようになりました。
発展すれば、人間は宇宙ステーションにいるロボットを感覚的に操作することさえ可能になることでしょう。
More Episodes
仏教の十二縁起と、キリスト教の楽園追放の類似性 イヴの原罪とアダムの原罪 ジョン・スチュアート・ミルの質的功利主義、ベンサムの功利主義からの逸脱 異なる3つの論理体系
Published 08/14/23
ポンペオ米国務長官が七月二十三日に、中国の人権抑圧・領土拡張・経済的不公正と、その理念的基盤であるマルクス・レーニン主義に対し、宣戦布告とも解釈できる演説を行ったことで、新型コロナウィルスで混乱の中にある世界は新冷戦時代へ突入することになりました。現代の世界には、エリート階級が政策決定の権限を独占する体制と、自由と民主主義を標榜する体制の二種類の国家に分類することができますが、中国は前者、アメリカは後者の正義を代表する国家だと言えるでしょう。
しかし、中国の不正義を糾弾したポンペオ氏のアメリカの中にも相矛盾する複数の正義があり、必ずしも一枚岩とは言えません。自由と民主主義を標榜する社...
Published 08/14/23
Published 08/14/23