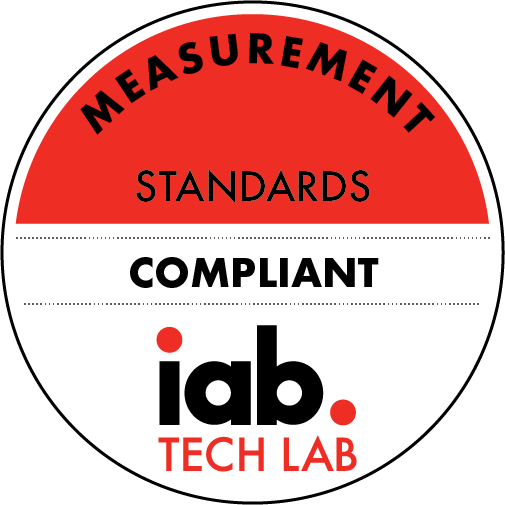174.2 第163話【後編】
Description
3-163-2.mp3
「あり合わせで用意しました。」
そう言って出されたのはハンバーガーだった。
「自分、奥にいますのでごゆっくり。」
マスターが奥に引っ込んだを見届けてふたりはそれを頬張った。
「うまい。」
京子も三波もその確かな味に唸る。
「このボストークって最近映えるとかで有名な店だろ。」
「はい。」
「この手の雰囲気重視の店って、どっちかっていうと味は微妙ってのが多いけど、ここは違うね。」
「そうでしょ。しっかりおいしいんです。」
「ランチですとかいってワンプレートのもん出されても、え?こんだけで1,000円するのって量の店もあるじゃん。でもほらこのハンバーガー、普通に大きいんだけど。」
「まかないっていうのもあるかもしれませんよ。」
「あ、そうか。」
「ってか肉がおいしいですよ。これ。よくみたら網で焼いてる。」
「本当だ。くそー…しっかしなんか悔しいな。」
「何がですか?」
「なんか女子とかカップルとかでキャッキャ言って映えばっかり気にされる店にされてんじゃん。」
「なんですか三波さん。私のことそのキャッキャしてる女子って言ってんですか。」
「いやそうじゃなくて。もっと俺らみたいなおじさんにも利用しやすい感じにしてくれって言ってるだけだよ。」
「そんなの構わずガンガン利用すれば良いじゃないですか。」
「出来るわけ無いだろ。」
「えーでもいろんな人が利用して、その店の雰囲気って良くなっていくと思いますよ。」
「なにそれ。」
「ほら私もよくわかんないですけど、ヨーロッパの方の老舗カフェとかBarっておじさんもおばさんも、あんちゃんねぇちゃんもいろんな人が利用してるイメージあるじゃないですか。そういったところって著名作家とか芸術家が足繁く利用していたりして、店としての格式が高いでしょ。」
「おう。」
「この店もそうなれば面白いと思うな。」
「そのためには俺みたいなおっさんが人柱となって積極的に利用するのも必要、ってか。」
「三波さんみたいな人だけだと困りますが…。」
彼は苦笑いした。
「いやぁ美味かった。」
ハンバーガーを平らげた三波は出されていたコーヒーに口を付けた。
「相馬と来たことあんのか。ここ。」
京子は首を振る。
「あいつ東京で何やってんのさ、実際のところ。」
「バイトって聞いています。」
「それは俺も聞いたことあるけど本当にそうなのか?海外留学して、現地バイトで食いつなぐってのは分かるけど、日本に帰ってきてバイトって…。あれか何か目指すものがあんのかな。」
「多分嘘ですよバイトって。」
「へ?」
「言えないことあるんでしょ。だからそこのところは私、敢えて聞かないようにしてるんです。」
「あ…そうだったんだ…。」
「こういうの私、慣れていますから。」
「慣れてるって?」
「私の父です。」
「あ、あぁ…。」
「父も絶対に嘘だってことを家族に言ってました。多分、父自身も家族が分かっていることを知っていたでしょう。父は家族をだまし公安としての任務に身を投じる。私や母は父が公安なんて知る由もない。父から見て善良な妻と娘。三人が三人、同じ舞台の上で役割を演じていた。」
「ってことは相馬も…と。」
「全く同じ仕事をしてるか分かりません。でも父も周もどちらも東京です。」
ーそうだよな。公安の親
More Episodes
3-183-3.mp3
ドローンが機動隊車両の上空に達したかと思うと、突如として激しい閃光が放たれた。次の瞬間、爆音とともにドローンが自爆し、その衝撃が車両に直撃する。
軽めの爆発音
爆発音は雷鳴のように周囲に轟き、もてなしドームを揺るがした。その音は商業ビルのガラスを震わせ、破片が空中を舞った。
吉川「伏せろっ!」
吉川がSAT隊員に大声で言った。
大きな爆発
車両の中に積まれていた火薬が誘爆した。炎が瞬く間に車両全体を包み込み、巨大な火の玉が金沢駅前を照らし出した。爆風は猛烈で、周囲の車両や建物に衝撃波が伝わり、商業ビルの窓ガラスが次々と割れて粉々に飛び散った。爆風は人...
Published 10/25/24
Published 10/25/24
3-183-2.mp3
特殊作戦群「こちら特殊作戦群、これよりアルミヤプラボスディア掃討のため現場に介入する。SATは援護を頼む。」
無線の一報が入った瞬間、戦場のすべての勢力が息を呑んだように思えた。
自衛隊の特殊作戦群が戦闘に介入する。
それは、当該部隊が創設され初めてのことである。しかも現場は日本。
すべての当事者が、その異様な光景に困惑し、動きを止めた。
片倉「特殊作戦群やと…。」
公安特課テロ対策本部の片倉がこれ以上の言葉が出ないようだった。
相馬「特殊作戦群…。」
駅交番で児玉と共に待機する相馬も、この部隊名称を呼ぶのが精一杯だった。
森本「特殊作戦群だと…。」...
Published 10/25/24