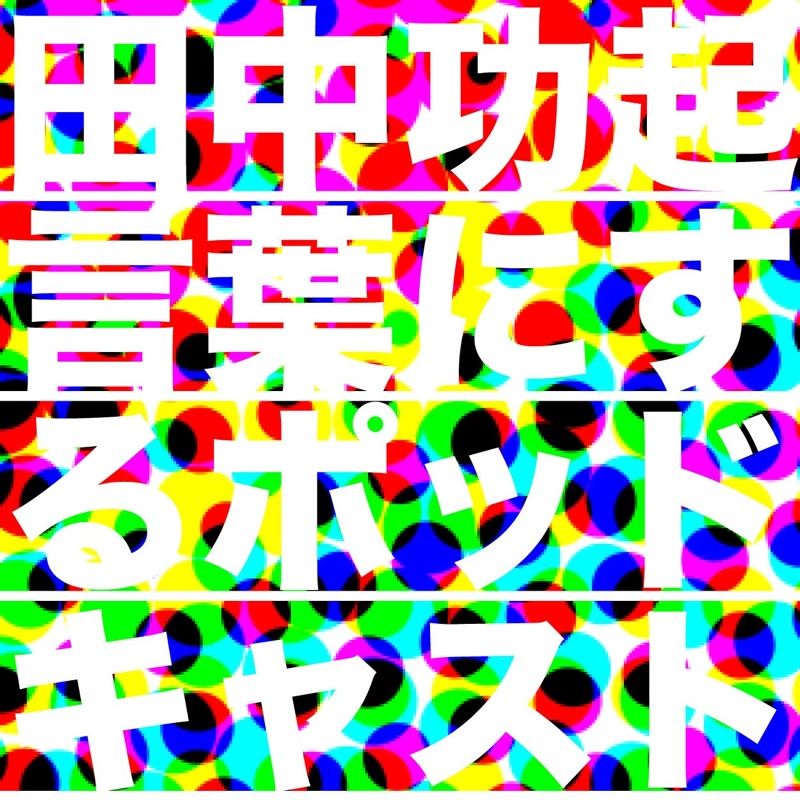Episodes
戦後アメリカ美術の背景には大衆文化(ビート・ジェネレーション)があり、ビートニクの背景には東洋思想がある。つまりコンテンポラリー・アートの背景にはそもそも東洋思想があるんだってことなんですね。だからぼくたちは、なにも表面的に日本的な表象を使わずとも、直にアート・ヒストリーに接続できる可能性がある。カズさんはそのように解釈します。
カズさんが「被害者ビジネス」と呼ぶ、マイノリティであることで優遇されてしまうことに安住するんじゃなく、同じ土俵でガチンコするためにぼくらにとってどういう態度が必要なのか。身が引き締まる話ばかりでした。
ではまた次回!
オリジナルの収録日:2009年8月20日
4/4
Published 12/19/09
日常のなかのノイズに気づくこと、それによって見えていた風景が変化していく。
作品の装いはカズさんのとぼくのとではまったく違いますが、その核となる考え方には共通点がたくさんあるんだなってことに気づかされました。
また話は、戦後アメリカ美術にやられっぱなし(?)の日本のアートの話にもなります。テリヤキチキンと精進料理という比喩をつかって、アメリカでの日本のアートの需要とその後の展開(?)について、するどいつっこみがまってます。ではじゃあ、どうすればいいのか、なかなか難しい問題ですけど、それについては最後のセッションを聞いてください!
オリジナルの収録日:2009年8月20日
3/4
Published 12/06/09
このセッションではぼくが「展覧会」という制度の問題について疑問を投げかけてます。ぼくがそこで考えていたことは制度を単に否定することではなく、そのなかにいてどのようにアーティストが自由を取り戻すかって問題でした。話は作品をめぐる経済のことにも発展します。でもどうも今回、舌足らずでうまく言葉にできていません。この問題、今後も継続して考えていきたいです。
オリジナルの収録日:2009年8月20日
2/4
Published 11/25/09
さて、第五回目はカルフォルニア・シリーズ第二弾ということで、LA在住のアーティスト、大城カズ(大城康和)さんをお迎えしてます。
ぼくがはじめてカズさんの作品を見たのは、いまはなきRelaxというカルチャー誌上ででした。ピンク色のマーシャル・アンプの積み上がっている作品で、それが実はキャンバスでできあがっている立体・絵画だってことを知って驚きました。
ぼくがカズさんに共感するのは制作に対する態度です。自分が立っている場所を受け入れ、できるかぎり妥協せず自分の感じているリアリティを形にする。アーティストならばかならず必要なことなんでしょうけれども、なかなかぼくもできてません。カズさんの制作・言葉からはぶれない確かななにかを感じます。
最初のセッションでは、「作ること」と「見せること」の違い、その矛盾をどう解決するかというカズさんの出発点について話してもらってます。
オリジナルの収録日:2009年8月20日
1/4
Published 11/14/09
最後は、せっかくだからLAの印象を、となおさんに言われて話してますが、いつの間にか映画の話に。ぼくらにとってはとても悩ましい存在です、映画は。
というわけでまた次回。
オリジナルの収録日:2009年8月1日
5/5
Published 09/30/09
ぼくがなおさんと話したかったひとつの理由に映画のことがあります。どんな映画が撮りたいのか、どうやって撮りたいのか、そんな話を前にもしたことがあって。
ぼくは映画をじぶんの娯楽としてたぶん位置づけているところがあって、そのへん、なおさんは映画をじぶんの制作の方法論として据えているところがあるので、この違いがなかなかおもしろくあらわれていると思います。
松本人志の新作「しんぼる」、まったく知りませんでした。日本ではもう公開してますね。ぼくも見たい。ちょうどさいきん「大日本人」がLAでは公開してました。
オリジナルの収録日:2009年8月1日
4/5
Published 09/29/09
パフォーマンス・ベースの作品をのちに見せる場合、もはやライブな経験は失われているので、付随するプロップやドキュメントを見せることになります。もはや失われたものを想像して見るっていうことがぼくにはどうも疑問でした。なぜならその場に居合わせていないひとには評価のしようがないものだから。
なおさんもぼくもなにかしらの行為を映像にして見せますが、上に書いたこととの違いをさぐって話してます。その後、なおさんの作品をめぐって、話はふくらみ、とくに夢の話はかなり興味深いです。じぶんとアレするってどういう夢なんでしょう!
オリジナルの収録日:2009年8月1日
3/5
Published 09/21/09
なおさんとの二回目のセッションです。
カリフォルニアのアーティストについて、カタログを見ながら話してます。ミニマリズムやコンセプチュアル・アートが東海岸から西海岸へ入ってくると、なにかプラスアルファの要素が加えられて変容している、ひとつべつのレイヤーが入っている、ってなおさんは言ってます。たしかにここに上げられているアーティストはそれぞれひとくせありますよね。
Charles Ray, Michael Asher, Chris Burden, Ed Ruscha
そのほかなおさんの友人のアーティスト: Jedediah Caesar, Kiersten Puusemp。
ぼくが途中で口走っているのは:Jason DodgeとPak Sheung Chuen
*なにかの電波をキャッチして変な電波音が入ってます。ご了承下さい。
オリジナルの収録日:2009年8月1日
2/5
Published 08/22/09
第四回目の今回は、LA在住のアーティストの廣直高さんをお迎えしてます。
せっかくなのでカルフォルニアのことを、ってなおさんが言ってくれたので、まずは彼自身の作品のことを絡めつつ、LAのアートについても話してもらってます。まだまだLAのことは知らないことがたくさんなので、とても興味深く聞きました。
ところで今回も機材の使い方がいまいち慣れていなく、録音レベルオーバーでところどころノイズが入ってしまいました。お聞き苦しくてすみません!
追記:保坂さんの回がまだ残ってますが、諸事情があってアップでいないので、もうしばらくお待ち下さい!
オリジナルの収録日:2009年8月1日
1/5
Published 08/19/09
こんにちは、田中功起です。今回はひとりで近況報告です。長坂常さんの「B面がA面にかわるとき」について話してます。メールアドレスも作りました(本編では言うのをさっそく忘れてます)。感想や間違いの報告、要望、あとはぼく自身への質問などもどうぞ!ポッドキャストで取り上げることがあるので、ラジオネームなどを添えてください。
[email protected]
よろしく!
Published 07/04/09
ひきつづき保坂健二朗さんとの三回目のセッションです。
ある鼎談で、保坂さんが「なにも頼まれなくてもやっているひと=アーティスト」と言っていたことをぼくは気になっていました。アーティストって何者なんだろう。保坂さんはどうそれをとらえているんでしょうか、そういうことについて話してます。失敗作を見せる勇気とそれを受け入れる目線という話もなかなかおもしろかったです。
補遺:
1,話の中にでてくる本はこれです。『キュレーターになる! アートを世に出す表現者』(フィルムアート社、2009)
2,あと興味のある方のためのキーワード:「宏観異常現象(こうかんいじょうげんしょう)」ぐぐってください。
3,中原浩大さんの参加した展覧会の正式なタイトルは「景観 もとの島」(仙台メディアテーク、2005)
4,ジュリアン・シュナーベルの映画「潜水服は蝶の夢を見る」の日本での公開は2008年でした。DVD、出てます。
オリジナルの収録日:2009年1月28日夜
Published 06/17/09
保坂健二朗さんとの二回目のセッションです。すみません。ずいぶん間が空いてしまいました。
ここでは一回目のセッションにひきつづき「書くということ」について話しています。単に新書や雑誌を否定するのではなく、新書でしかできないことや一般誌でしかできないことの可能性について保坂さんが話しています。つまり純粋な批評や学術論文ではないあり方でもテキストは書けるし、そうして伝えられていくこともある。そうして話は今回の肝、広告とアートの関係について及びます。悩ましい関係がこのふたつにあって、これはぼくが事前に用意した内容ではないですが、期せずして興味深い話に及びます。保坂さんのフレキシブルな発想にやられっぱなしでした。ぼくたちが自覚的であるかぎり、可能性はどこにでもあるってことですよね?
ぼくが話の中で「中島さん」と言っているのは中島哲也さんです(『下妻物語』『嫌われ松子の一生』はいずれもすばらしい)。
保坂さんが言っていたのは立花文穂さん。話のなかで出てきているのは「MOTアニュアル 解きほぐすとき」(東京都現代美術館、2008)のことです。立花さんの展示はとてもおもしろかったです。
オリジナ...
Published 05/26/09
第三回目の今回は、東京国立近代美術館の保坂健二朗さんと話しています。同級生の活躍ってなんだか気になるもので、保坂さんは同級生です。たとえば本上まなみさんも同級生ですね。
保坂さんは2008年に「建築が生まれるとき ペーター・メルクリと青木淳」と「現代美術への視点6 エモーショナル・ドローイング」というふたつの展覧会を企画していて、いずれもとても興味深いものでした。ちなみに「建築が〜」のカタログでは、青木淳さんについてのぼくのテキストも掲載されています。
まずは批評および書くことについて、その困難さも含めて、ワインを飲みながら話してます。ちなみに今回から録音機材がアップグレードされたのですが、どうやら録音レベルが低かったらしく、以前とくらべて音量が低めです。すみません。
オリジナルの収録日:2009年1月28日夜
Published 04/25/09
粟田大輔さんと話す、その4
最後のセッション。ここでは話題をかえてポッドキャストについて話してます。粟田さんもポッドキャストをやろうと思っていたらしく、そのときのことや、最後には新しい批評誌の提案まで「言葉にする」ことをめぐって話してます。
ではではまた次回。
オリジナルの収録日:2008/12/28 *録音機材の問題で聞きづらい部分がありますが、ご了承ください。
Published 02/07/09
粟田大輔くんと話す、その3
三回目のセッションでは、ぼくが粟田さんの質問に答えています。豊かな現実の出来事と作品はどういう関係にあるのか、ということから、作品とそれを作ったぼく自身の身体的なリアクションのことまで、つつみ隠さず話してます。
オリジナルの収録日:2008/12/28 *録音機材の問題で聞きづらい部分がありますが、ご了承ください。
Published 01/31/09
粟田大輔くんと話す、その2
このセッションでは河原温さんの作品をめぐって、その作品をアーティストの身体との関係から話してます。一見、身体的な表現とはほど遠く見える河原さんの作品を、ぼくたちがいやおうなく縛られているこの身体があくまでベースとなって生み出される身体的な作品であるというふうにとらえています。
ぼく、田中がちょっと話しすぎですが、どうぞよろしく。
オリジナルの収録日:2008/12/28 *録音機材の問題で聞きづらい部分がありますが、ご了承ください。
Published 01/17/09
粟田大輔くんと話す、その1
第二回目の今回は、粟田大輔くん(美術解剖)をお迎えしてお送りします。きっかけは「奥村雄樹くんと話す、その4」のなかでぼくと奥村くんが飲み会での粟田くんの発言を肴にしゃべってしまったこと。明文化されていないものをとりあげるのはあまりよくないのでは、という粟田くんの指摘を受けて、そのときにおおざっぱに分けてしまった作家論と作品論の区分けについて、もういちど考えてみるというのが今回の目的です。
実際、ぼくたちの会話は、作者の言葉はどういう位置にあるのか、どこまでを作品として考えるのか、そうした作り手と作品の分かちがたくある関係をめぐって進められた。
全4回、どうぞお聞き下さい。
オリジナルの収録日:2008/12/28 *録音機材の問題で聞きづらい部分がありますが、ご了承ください。
Published 01/16/09
奥村雄樹くんと話す、その4
なにかを感じて、それをひとまずはじぶん自身から突きはなす、ためにいったん忘れる。解除する。それがもういちど置きなおす。でもそれがどういうふうに置かれるか、その再配置を決定する判断の中に、最初の感覚が使用される。と、とっても抽象的だけれども作品制作のプロセスはこうした個人的な「感覚」をどうあつかうかにって決まってくるように思う。
奥村「批評とは言及対象(作品)それ自体がいったい何なのかを記述することである」
ぼくたちは作品そのものを評価するのか、それともアーティスト個人を評価するのか。つまり作品論が大切なのか、アーティスト論が大切なのか(つまりアーティストがつくった作品の流れや考えたことが大切なのか)。
話はつきないけど、ここでひとまず今回の会話は終わります。最後まで聞いてくれたみなさん、ありがとう。また次回。
Published 10/02/08
奥村雄樹くんと話す、その3
偶然に作品はできないけれども、作品のなかには偶然が入っている、ということがどうやら必要なことらしい。というのはぼくも奥村くんもわかっている。でもそれはなぜなんだろう。
その偶然というものを「ノイズ」ととらえ直してもいいかもしれない。
作品のなかに含まれるノイズ。筋道立てたすものごとを進みにくくさせるノイズ。
奥村くんは2006年の時点で、そのノイズを「ナラティヴ」といい、そこにぼくが当時、否定的に思っていたつぎのものを含めていた。政治的文脈、歴史的文脈、シンボリズム、メタファー、そして個人の物語(これはぼくが追加したものだけれども)。偶然、ノイズ、ナラティブはとりはらうべきものじゃなくて、それによって作品制作が豊かになることもある、それがそのころの結論だった。でも...。
田中「プロセスが複雑だとなかなか作品はできあがらない」
奥村「偶然とは、僕たちの恣意的な制御を超えたもの」
Published 10/01/08
奥村雄樹くんと話す、その2
たとえば自分とはなんだろうか、たとえばなぜ作品の中に日常の風景が出てくるのか、いやそもそも日常と非日常の違いがあるのかないのか、などなど。つづけて録音されたこの二回目のセッションでは、ノーカットの会話特有の矛盾もちょっと出てきますが、さらに白熱(?)していきます。
田中「ぼくにとってはこの日常の光景は、自分の作品がそこからの地続きであるために必要なんだ」
奥村「そもそも日常、非日常の区別はなく、すべては同じであると思う」
Published 09/30/08
奥村雄樹くんと話す、その1
今回は、批評活動もしているアーティスト、奥村雄樹くんといままでのぼくたちのなかでの会話ややりとりをまとめつつ話してみた。 たとえばぼくたちはこの世界をどのようにとらえてそれを作品に反映させているのか、とか。そうしたことが話の中心になってます。
なぜ、まず最初に奥村くんと話したかったかというと、ぼくたちはいちどゆっくりと時間をかけてメール書簡を交換したことがあり、つくることのプロセスをわりとざっくばらんにやりとりできたんですね。奥村くんはいつもものごとを整理したうえで返信をくれて、それが彼の作品のつくりかたにもなんとなく反映されているようにも思いました。なぜなら奥村くんの作品には、いつもシンプルなルールがあって、でもそこからはずれることをよしとしない厳密さもあって、そのガンコさ加減がなぜか作品の自由度にもつながっているように感じられて...。厳密さをシンプルなことに適応することでしかたどりつけない自由さというか。
全体の話は三時間ちかくにわたり、というわけでとても長いですが、
ではではどうぞゆっくりお聞きください。
Published 09/29/08